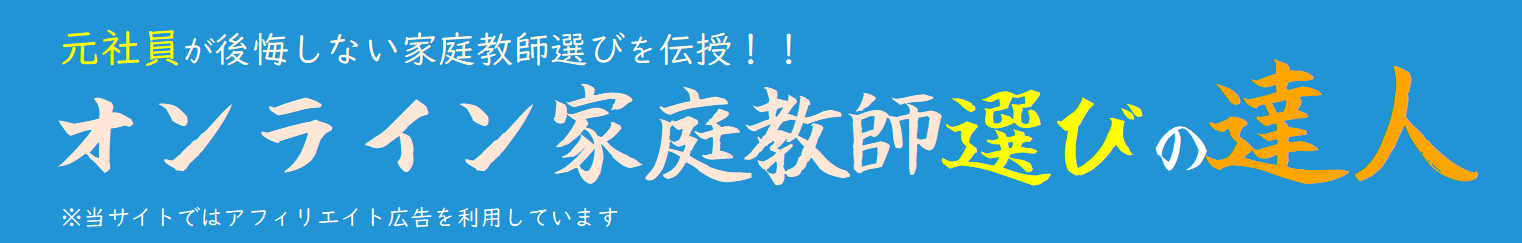- 通知表で2や1がついてしまった・・
- 勉強しているはずなのに成績が悪い・・
- いくら言ってもやる気を出さない・・
中学生になると、内容が難しくなるため、できる子とできない子の差がついてしまいます。
勉強ができなくなると、卒業後の進路に影響するため、親としては焦ってしまもの。
でも、子どもも反抗期で、「勉強しなさい」と言ってもきかないのよね。
「なんとかしたいけど、どうにもできない・・」と悩む親御さんが多いです。
そこでこの記事では、以下の点についてまとめました。

オンライン家庭教師の達人(達人)
この記事を書いた人
10年に渡る家庭教師派遣会社の勤務で、以下の仕事を担当。
- 100名以上のプロ家庭教師指導
- 1000件以上の家庭教師契約
- オンライン家庭教師部門の立ち上げ
オンライン家庭教師に関する内容を中心に、勉強に悩むご家庭へ、お役立ち情報を発信します。
詳しいプロフィールはこちら
お子さんを褒めて自尊心を育てたり、できない原因を突き止めて第三者に依頼するなど、親にできることは少なくありません。
直接勉強を教えるのは難しいですが、間接的に関わることはまだまだできますよ。
この記事を読めば、中学生のお子さんが成績を伸ばすために、親はどうすればいいかが分かります。
目次
中学生で「成績が悪い」ってどれくらい?

「勉強ができない」という状態は、具体的にはどういう成績なのでしょうか。
中学校では、通知表で5段階評価を使い成績をつけます。
真ん中の「3」未満である、「2」や「1」がついてしまうと、成績が悪い状態だと言えます。
実際、「1」や「2」がつくと、以下のような危険が。
- テストの点数が半分以下になりがちで、基礎基本が理解できていない
- 「自分は勉強ができない」と感じ、やる気がなくなる
- 通知表がオール2以下だと、高校進学が難しくなる
この状態で受験シーズンを迎えると、ばん回はかなり厳しいです。
早めに手を打たないとまずそうだね・・
勉強ができないお子さんの2つのパターン

成績が悪いお子さんには、2つのパターンがあります。
単純な分類ですが、パターンによって打つべき手が異なるので、どちらなのかをはっきりさせましょう。
そもそも勉強をしていない
当たり前の話ですが、勉強をしていないために成績が悪いパターンです。ただし、これには色々なタイプが。
- 勉強が嫌いだからやろうとしない
- 部活や習い事で忙しく、勉強する時間や体力が無い
- 主体性がなく、どう勉強したらいいかわからない
どの理由にせよ、中学生ともなると、親御さんが「勉強しなさい」と言うだけで解決できる状況ではありません。
生活環境や接し方を変えたり、第三者の力を借りる必要があります。
勉強しているのに成績が悪い
それなりに時間をかけて勉強をしているのに、なぜかテストで点数が取れないケースもあります。
実は、勉強の方法のなかには、成果に結びつきにくいものも。代表例として2つ紹介します。
綺麗なノートまとめ
単元の内容を綺麗にノートにまとめるのが得意なお子さんがいます。
特に女の子のお子さんに多いですね。
しかし、結局大切なのは「問題が解けること」。
ノートをまとめることが目的になっており、問題演習が足りていないと、「勉強しているのに点数が取れない」ということになります。
アリバイ勉強
宿題を嫌々こなす場合、
- 問題集の解答を写す
- とにかく手を動かしてノートに書くだけ
という勉強になることも。
このような、「勉強をやった」という事実を作るために作業をし、何も理解していない勉強は、「アリバイ勉強」と呼ばれたりします。
これだと点数は取れないだろうね・・
これらに当てはまってないのに、いくら頑張っても理解できていない・・という場合は、学習障害などの可能性も。
学習障害が疑わしい場合の対応は、こちらでまとめています。
勉強ができない中学生、将来はどうなる?

勉強ができないまま高校受験を迎えると、どのような将来が待っているでしょうか?
可能性としては、以下のパターンが考えられます。
- 地域最底辺の高校に進学する
- 定時制・通信制の高校に通う
- 中卒で働く
地域最底辺の高校に進学する
一番多いのが、地域で最も偏差値の低い高校に進学するパターン。
多くの地域には、オール2以下レベルでも進学できる高校があり、そこに通うことになります。
ただし、このような学校は素行に問題がある生徒も多く、暴力沙汰などのトラブルに巻き込まれる危険があります。
できるなら、そういう高校には通わせたくないわね・・
また、大学進学をする生徒はほとんどおらず、就職や短大、専門学校に進むパターンが圧倒的。
大学に行く気が無いならば問題ありませんが、中位層の高校に進学するのに比べ、将来の選択肢が狭くなります。
定時制・通信制の高校に通う
定時制や通信制の高校は、登校日数が足りないお子さんが通うイメージがあるかもしれません。
しかし、学力が極端にないお子さんが入学するケースも。
全日制とは違い、自分のペースで学習ができるのが強みですが、進学に向けたサポートや環境という面では劣ります。
お子さん本人に強い意志がないと進学は難しめです。
中卒で働く
最近ではほとんどありませんが、そもそも高校に進学しないという選択肢も。
ただし、最近ではアルバイトでも高校生でないと採用しないことも多く、昔に比べ中卒で働ける選択肢が狭くなっています。
中卒で働ける選択肢の例として、以下のものが挙げられます。
- 工事現場作業員
- 工場作業員
- 介護職
どれも体力的にハードであり、また、年を重ねても昇給は見込みにくい傾向が。
出世できる可能性もありますが、大卒社員に比べて、給与や昇格にハッキリ差をつけられるのが普通です。
病気や障害が疑わしい場合はどうする?

いくら真面目に勉強しても、問題が解けないお子さんのなかには、学習障害などの診断をされるケースがあります。
その場合は、お子さんの特徴・症状に合わせて勉強をしないと、ほとんど理解できません。
障害が疑われる特徴があれば診察を受ける
発達障害に詳しいLITALIKO発達障害というサイトでは、学習障害の特徴が紹介されています。
国語に関するチェックポイント
・形の似た文字を読み間違える、文末などを自分の想像で変えて読む
・左右反転の鏡文字を書くことがある
・文章のルールの理解が難しい(主語が抜ける、「てにをは」の誤りなど)
数学に関するチェックポイント
・暗算が苦手、数字を読み間違える
・+-などの記号の意味が記憶できず、計算できないことがある
・算数の応用問題・証明問題・図形問題が苦手
英語に関するチェックポイント
・英単語を見ても理解できないことがある
・音読するときに、英単語の発音で詰まる
・書き写しの際にアルファベットが抜ける
LITALIKO発達障害|中学生になって学習障害と分かったら?塾の選び方や障害タイプ別の勉強方法
このような特徴がみられる場合は、診察を受けてみるのもよいでしょう。
学習障害・発達障害を診断してもらうには、基本的には小児科や児童精神科、小児神経科を受信するのがよいと言われています。
こちらのサイト(発達障害(ADHD、自閉症、学習障害)-受診するのは精神科?小児科?|オンライン発達相談サービスkikotto)にわかりやすくまとまっています。
お子さんの特徴に合わせた学習法を実践する
学習障害や発達障害と診断された場合、お子さんに合う学習方法をアドバイスされることが多いです。
一般的な学習方法にこだわらず、お子さんが理解しやすい方法で、ひとつづつ身に着けてもらいましょう。
なお、親子二人三脚で勉強するのも良いですが、時間的・体力的に難しい場合は、第三者に頼るのがおすすめ。
この場合に頼れるところとしては、以下の3つが挙げられます。
- マンツーマンで勉強をみてくれる家庭教師
- 学習障害のお子さん対応に力を入れている塾
- 放課後等デイサービス
このようなサービスが近くにないか探してみましょう。
発達障害サポートが可能な家庭教師を選ぼう
発達障害のサポートにも対応している家庭教師会社もあります。
たとえば、「家庭教師ファースト」では、ADHD,LD,ASDなどの特徴に合わせて、お子さんの勉強をフォロー可能。
ファーストでは入会前に実際の先生で体験授業ができます。お子さんの特徴やこちらの要望を伝え、上手く応えてくれそうか体験してみましょう。
勉強できないお子さんに親がやれること

中学生ともなると、親御さんが直接勉強を教えたり、強制的に勉強をさせるのも難しくなります。
だからと言って諦める必要はありません。以下の方法で間接的に影響を与えることは可能です。
自尊心を満たす
勉強を頑張るためには、嫌なことにも取り組む心の強さが必要。そのためには、自分に対する自信(自尊心)が重要です。
普段から親にガミガミ言われると、自尊心が傷つき、頑張る意欲が湧きません。
そこで、普段の生活で本人が頑張っていることなどを積極的に褒めてみましょう。
部活など、勉強以外のことでも構いません。
ただし、無理やり褒めると、媚びる感じになるので注意が必要みたいだね。
勉強以外のことがきっかけでも、自分に自信がつけば、向上心を持てるようになります。
将来について話をしてみる
中学卒業後の人生について、お子さんと話してみることも重要。
今の成績のままだと、自分が将来どうなるのかを理解させましょう。
- 環境の悪い高校にしか進学してもよいか
- 定時制や通信制しかに通ってもよいか
- 大学進学をせず、高卒で働くことになってもいいか
- 中卒で働くなら、選べる仕事の中でやりたいことはあるか
成績が悪いと、選択肢が狭まるのを実感させることが大切です。
お子さんに「今のままだとヤバい」と感じさせれば、勉強への意識が変わりますよ。
大卒・高卒・中卒の年収の違いも理解させる
露骨ですが、最終学歴によってどれくらい平均年収が違うかを理解させるのも良いです。
厚生労働省の発表している、平成28年賃金構造基本統計調査の結果によると、
- 大卒 371万円
- 高卒 262万円
- 中卒 244万円
と、かなり差があります。
高卒と中卒だけでも年間20万円変わり、それが40年続くと、800万円くらいの差がつく・・などと説明しましょう。
それによって、「今頑張らないと後悔する」と実感してくれます。
ガミガミ言わない
中学生のお子さんに、直接「勉強しなさい」と言っても効果は薄いもの。
叱り口調で話しても、反発されたり、かえってやる気をそいでしまうことが多いです。
この時期のお子さんは、親よりも、本人が信頼している第三者
- 学校の先生
- 親戚、近所のお兄さんお姉さん
- 塾や家庭教師の先生など
に話してもらう方が響きます。
周りの人たちの力を借りるのがいいのね。
親の立場としては、「勉強しなさい」と言うかわりに、勉強に集中しやすい環境を作る方が効果的です。
お子さんの部屋に、勉強に取り組みやすい机やいすを用意したり、リビングで勉強する間はテレビを消すなどの対応が考えられます。
無茶な目標を押し付けない
勉強ができないお子さんは、やる気もないのが普通です。
そんな子がやる気を出すには、「小さな成功体験」を積み重ねて自信をつけることが重要。
そのためには、レベルが低くとも、達成できそうな目標を課すことが大切です。
通知表が「1」なら30点を目指して「2」を狙い、その次は50点を目指して「3」を狙う・・というのが現実的ですよ。
ごくまれに、理想が高いあまり、厳しい目標を押し付けてしまう親御さんも。
もともとやる気のないお子さんは、目標が高すぎると、「頑張っても無理なら、初めから頑張らない方がいい」と、本末転倒な考えになります。
親の理想や見栄を子どもにぶつけてないか、振り返ったほうがいいかもですね。
プロの力を借りる
お子さんを前向きにさせられれば、自然とやる気が上がります。
そのうえで、中学生以上なら、教えるのはプロに任せた方が無難です。
内容が難しくなるうえ、親子喧嘩の原因になるので、直接教えるのは難しいですよ。
勉強ができないお子さんなら、集団授業の塾はオススメできません。
マンツーマンで教えてもらえる家庭教師に依頼し、着実に学力を伸ばしてもらいましょう。
家庭教師に丸投げはNG
勉強が苦手なお子さんの場合、先生には状況を詳しく伝えましょう。例えば、以下の情報が重要。
- やる気がなくて勉強してないのか、勉強しているのに成績が悪いのか
- いままでどんな勉強をしてきたのか
- 学習障害がある場合は、その特徴と推奨された勉強方法
また、「成功体験を積ませて自信をつけさせてほしい」とか、「将来の話をして危機感を持たせてほしい」など、細かい要望も伝えましょう。
色々な情報があったほうが、先生も最適な指導方法を見つけやすくなります。
反抗期のお子さんには間接的なサポートを
お子さんが勉強ができないのには必ず理由があります。その原因を突き止めてあげることが大切。
勉強を教えることは塾や家庭教師でもできますが、原因を探るのは毎日顔を合わせる親御さんが適任です。
そして、第三者に教わる必要があるなら、マンツーマンで対応してくれる家庭教師を頼るのがよいでしょう。
中学生のお子さんには、間接的なサポートを心掛けましょう。