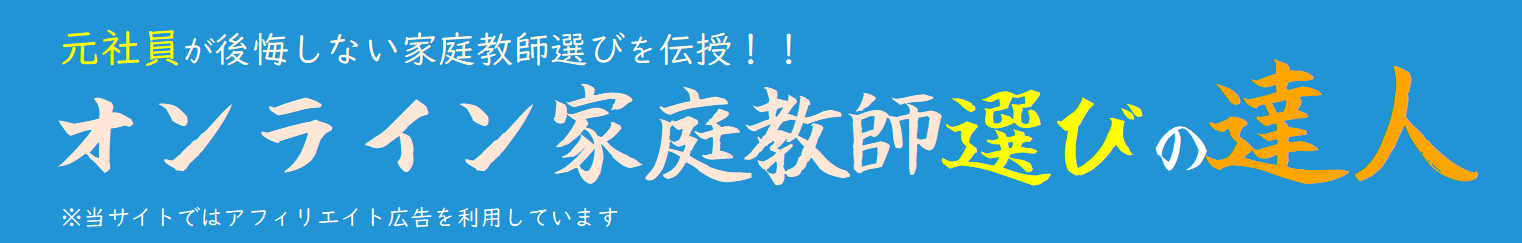- 子どもが勉強できないのは親の遺伝?
- 成績が悪いのは育て方が原因?
お子さんの成績が悪いと、遺伝や育て方に原因があるのかと気にする親は多いもの。
勉強が苦手だと、進学や就職の選択肢が狭くなり、お子さんの収入や社会的な評価も低くなる危険もあります。
その原因がもし親にあるんだったら・・と悩むのは苦しいですよね。
少しでも勉強ができるようになってほしいです・・
そこでこの記事では、以下の点についてまとめました。

オンライン家庭教師の達人(達人)
この記事を書いた人
10年に渡る家庭教師派遣会社の勤務で、以下の仕事を担当。
- 100名以上のプロ家庭教師指導
- 1000件以上の家庭教師契約
- オンライン家庭教師部門の立ち上げ
オンライン家庭教師に関する内容を中心に、勉強に悩むご家庭へ、お役立ち情報を発信します。
詳しいプロフィールはこちら
お子さんが勉強ができるかどうかは、遺伝などよりも、親の関わり方が大きく影響するもの。
この記事を読むと、お子さんが勉強嫌いになるNGな言動や、お子さんを勉強好きにさせる方法が分かります。
「子どもが勉強できない」という悩みを解決する助けになりますよ。
目次
子どもを勉強嫌いにさせる親のNG言動

特に年齢が低いうちは、親の関わり方によって、勉強が好きになるか嫌いになるか決まります。
子どもが勉強嫌いにさせてしまう言動をしていないか、振り返ってみましょう。
勉強を強制している・ガミガミ言う
「勉強をしなさい」と毎日怒ったり、ガミガミ言うと、勉強に対して嫌な気持ちになってしまいます。
お子さんが勉強をしないと、どうしてもイライラして叱ってしまうもの。
しかし、ただ怒りをぶつけるのではなく、接し方を工夫して、うまく勉強を促したいところです。
勉強を通じて褒められない・自尊心が育たない
特に幼い頃は、親からの褒め言葉が勉強へのモチベーションになります。
お子さんは、良い成績を喜ばれ・褒められる経験を通じて、自分に対する自信(自尊心)を身につけるもの。
勉強して褒められる経験が、嫌なことでも頑張る精神的な強さを育みます。
逆に、問題が解けずに叱られたり、悪い成績をガミガミ言われると、お子さんの自信や精神的な強さは育ちません。
それどころか、「嫌なことから逃げたい」と考えるようになります。
干渉しすぎてストレスを与える
期待が強すぎたり、親自身のプライドのために勉強させようとすると、お子さんに大きなストレスを与えます。
以下のような傾向がある場合は注意が必要です。
- 勉強を教えるときに、「早く問題を解け」とプレッシャーを与える
- 親の理想像を押し付け、小さな成功や成長を褒めない
- 本当に勉強をしているかを疑う
これは、親の思いが子どもにプレッシャーやストレスを与えている状態。
これが続くと、反抗から非行に走ったり、精神的に自立できなくなるなどの悪影響を及びます。
勉強嫌いになる以上の問題を生みそうだね。
「うちの子は勉強ができない」と周りに吹聴する
大人同士の会話では、謙遜の意味で「うちの子は勉強ができなくて・・」と言ってしまうケースも。
優秀なお子さんの親御さんと話すときに、ついつい言っちゃいます。
謙遜するのは日本人の美徳ですが、それをお子さんの目の前で言うのは、やはりよくありません。
「自分は勉強ができないんだ」と感じ、頑張ろうという気力を奪います。
なかには「見返してやろう」と奮起することもありますが、そうなるかは賭けです。
お子さんを傷つけてまで、わざわざそんな危険を冒すべきではありません。
子どもに関心を向けない
「ガミガミ言うのはダメなら、何も言わないでおこう」という考えもNG。
関心をむけられないと自尊心が満たされず、勉強を頑張ろうという気力が湧きません。
勉強に取り組む様子を褒め、努力を認めてあげましょう。そのうえで、明らかにサボっている時には、声をかけるべきです。
色々なアプローチで、お子さんのやる気を上げましょう。
勉強ができる子の特徴とポイント

勉強ができる子とできない子には、色々な違いがあります。その中でも大きいのは以下の点です。
- コツコツ努力できる・言われなくても勉強できる
- 自分なりの勉強方法が確立している・自分で考えて勉強ができる
コツコツ頑張るためには、意欲と自信が大切
言われなくても地道に勉強を続けてもらうには、まずはやる気が重要。
モチベーションは何でもかまいませんが、勉強を頑張りたい・頑張らなければいけないと自覚してもらう必要があります。
将来の夢を叶えるため、希望する学校に進学するため、が王道ですね。
お子さん自身が、自分への自信を持つことも重要です。
「自分は努力すればできるはず」という信念があれば、勉強を頑張り続けることが可能。
そのためには、お子さんを褒めてあげたり、頑張りを認めてあげましょう。
勉強方法が分からない場合は教えてもらう
勉強方法を確立させるには、自分に合う勉強方法を見つける必要があります。
筋の良いお子さんは、学校の授業を通じて自然に身に着けますが、そういうケースばかりではありません。
自分に合った方法が分からない場合は、プロに教えてもらうのが一番。塾もしくは家庭教師の先生に相談しましょう。
1対1になる家庭教師の方が、より細かくアドバイスができますよ。
子どもを勉強好きにさせる3つの方法

まずは、勉強嫌いにならないよう接することが大切。そのうえで、勉強好きになるように関わることも重要です。
お子さんの成長度合いによっても変わりますが、まずは基本的な3つのポイントを紹介します。
自発的に「勉強したい」と思わせる
「こうなりたい」という理想像を持たせ、「そのためには勉強が必要」と思わせると、自発的に勉強に取り組みます。
色々なパターンが考えられますが、代表的なものでは以下が挙げられます。
- 将来の夢(希望する仕事など)を持たせる
- 高得点が取れるのを当たり前にして、「自分は勉強ができる」と思わせる
- 中卒や高卒だと収入が少ないことを理解させ、進学や就職を目標にさせる
- 成績が悪いと、荒れている学校にしか進学できないことを理解させる
- 尊敬する先輩や入りたい部活をもとに志望校を決めさせる
このように間接的に導くことで、ガミガミ言わずとも、自発的に勉強します。
自尊心を育てる
単純に、「勉強を頑張る→褒められる」というサイクルを作り、自分への自信を育てることも有効。
努力して褒められることで、自尊心が育ちます。これによって勉強から逃げずに立ち向かえるようになります。
日ごろの姿勢を褒めてみたり、第三者の前で褒めるなど、色々なやり方があるみたいね。
褒め方にもテクニックがある
ビジネススキルの一つとして、褒め方のノウハウがありますが、お子さんを褒める場合にも応用可能。
「どうやって褒めたらいいか分からない」という親御さんは、一度学んでみる価値アリです。
わかりやすく教えてもらう
教え方によって理解のしやすさは大きく変わるもの。
親が何回教えても分からないことを、塾や家庭教師の先生なら一発でわかる・・なんてことはザラにあります。
親御さんが教えても上手くいかないなら、やはり教えるプロに任せた方がいいです。
プロに教わって一気に成績が伸びるケースは珍しくないですよ。
勉強好きにさせる関わり方・小学生編

ここからは、学年別のコツを具体的に紹介します。
小学生のうちは、親の言うことを素直に聞くので、直接的に関わりやすい傾向が。以下の点を意識しましょう。
勉強する習慣をつける
学校からの宿題や、市販のテキストなどで、必ず毎日勉強する習慣をつけましょう。
中学生になると、「勉強しなさい」と言っても素直に聞きません。小学生のうちに毎日勉強するのが当たり前にさせることが重要です。
小学生(特に低学年)のうちは、親御さんが教えてあげるのも効果的。
正解したり、宿題が終わったら褒めてあげ、自信をつけさせましょう。
小学校低学年までに、「勉強すると認めてもらえる」という実感を持たせるのが大切ですよ。
好奇心を伸ばす
お子さんの知的好奇心を伸ばすことで、自ら調べ物をするようになります。
その経験は、「知ることが楽しい」と実感させるもの。お子さんを自然に勉強に向かわせるモチベーションにもなります。
お子さんが何かに興味を示したら、以下を心掛け、お子さんの知的好奇心を育みましょう。
- 「どうして?」「これは何?」などの質問を否定しない
- 興味を示したことには一緒に考えてあげる
- 図鑑を与えたり、実際に学べる場所へ連れ出してみる
小学生のうちは、親の対応がお子さんの知的好奇心に大きく影響します。親御さんも忙しいですが、できる限りお子さんに向き合いたいところです。
読書の楽しさを伝える
知的好奇心を育てるのと同じくらい、読書の習慣をつけることも重要。
読書によって、勉強に必要な集中力や語彙力、読解力や想像力など色々な力が伸びます。
小学校低学年のうちは読み聞かせも効果的ですが、親が自ら読書をする姿を見せるのも悪くありません。
「子どもは親の言うことは聞かないが、行動は真似をする」と言われます。
親が日常的に読書をしたり、色々な本が家にあると、お子さんも読書が趣味になることが多いです。
勉強好きにさせる関わり方・中学生編

中学生になると、反抗期に入るため、親御さんが直接できることは限られます。
お子さんのやる気をそがないようにしたり、間接的に影響を与える関わり方が大切です。
勉強しやすい環境を整える
自分の部屋など、勉強に集中できるスペースを用意しましょう。
自分の部屋や勉強机で集中できるタイプや、家族がいるリビングの方が集中しやすいタイプなど、お子さんによって違いがあります。
様子を見たり、本人に直接聞くなどして、勉強しやすい環境を作りましょう。
希望する文具や参考書を用意するのもよさそうだね。
塾や家庭教師を過信しない
中学生だと、親が教えるのも難しく、塾や家庭教師を始めることが多いです。
親御さんのなかには、「塾に入れれば安心」とタカをくくってしまうことも。しかし丸投げは危険です。
そもそも、お子さんの成績・やる気によって、塾と家庭教師どちらが合うかが変わります。
- 成績が平均以上で、やる気もあるお子さんは塾
- 成績が平均以下、勉強が嫌いなお子さんは家庭教師
特に、学校についていけないのに集団塾に入ると、塾でもついていけず、成績は上がりません。
勉強が苦手なら、家庭教師の方が合いますよ。
>>塾派か家庭教師派か見分けるポイント・失敗しない家庭教師の選び方
家庭教師を始めるときの注意点
勉強ができない子が家庭教師を始める場合は、状況や、要望を細かく伝えましょう。
- やる気がないので、やる気を伸ばしてほしい
- 親が教えても理解できないので、噛み砕いて教えてほしい
- 集中力がないので、こまめに休憩してほしい
など、日ごろからお子さんを観察し、どう接するのがよいかを伝えることが重要。
先生としても、スタート時点での情報が多いほど、ベストな方法が判断しやすくなります。
やる気を削がない
中学生になると反抗期に入るため、親御さんの発言に反発することが多いです。
「勉強しなさい」と親に叱られ、「やろうと思ってたのにやる気なくなった」と反論する・・などのプチ喧嘩がよく起こります。
怒りの感情のままにぶつかるのはよくありません。
「勉強しなさい」「なんで成績悪いの?」のような責める言い方は避け、
- 高校受験について意識させる
- 頑張ったときには褒める
- 第三者を通じて褒める
などの方法で、間接的にやる気を高める作戦をとりましょう。
親の年収や学歴より、大切なのは関わり方
親の年収や学歴が、子どもの学力に影響すると言われることがあります。
個人的には、それよりも、子どもへの関わり方が大きな影響を与えるのではと思います。
自尊心を育て、やる気を伸ばすことが大事ってことね。
「子どもが勉強できないのは親のせい・・?」と悩むなら、お子さんへの接し方を変えることにエネルギーを注ぎましょう。