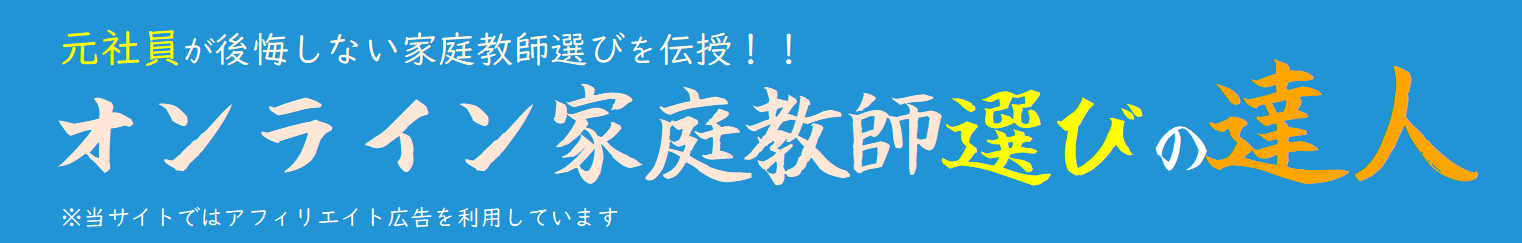「子どもが勉強できない・・」と悩む親は少なくありません。
親が言っても全く勉強しないケースや、勉強しているのに成績が悪いケースなど、色々なパターンがあります。
成績が悪いと、進路や将来に悪影響が及びます。
親だけが焦ってケンカになることもあるのよね・・
大切なわが子の幸せを願うからこそ、「手遅れになる前になんとかしたい」と願うのも無理はありません。
そこでこの記事では、以下の点についてまとめました。

オンライン家庭教師の達人(達人)
この記事を書いた人
10年に渡る家庭教師派遣会社の勤務で、以下の仕事を担当。
- 100名以上のプロ家庭教師指導
- 1000件以上の家庭教師契約
- オンライン家庭教師部門の立ち上げ
オンライン家庭教師に関する内容を中心に、勉強に悩むご家庭へ、お役立ち情報を発信します。
詳しいプロフィールはこちら
お子さんが勉強できない理由が分かれば、対処も十分に可能。
親の言動が原因になっている場合は、親御さんも行動を変えましょう。
この記事を読めば、お子さんが勉強できない理由と対策が分かります。お子さんの成績を上げるための一歩を踏み出せるでしょう。
子どもが勉強できない・やらない理由

お子さんの成績が悪い理由には、色々なものがあります。
代表例を以下に挙げるので、当てはまるものがないか確認してください。
目標がなく、勉強をする意欲が湧かない
まず、勉強を頑張る目標があるかどうかで、モチベーションが大きく変わります。
勉強を頑張る目標としては以下の例があります。
- なりたい職業・進学したい高校
- 学校内の順位
- テストの目標点
一番は、職業や志望校が決まっていること。これによって目標成績を決められます。
逆に、それがないと、勉強を頑張る目的が生まれず、なかなかやる気が上がりません。
勉強する習慣がない
小学校のうちに毎日勉強をしていると、勉強するのが当たり前の生活リズムが作れます。
習慣がつけば、親御さんが何も言わずとも自ら勉強しますよ。
その一方、中学生なると、親の力だけで習慣をつけさせるのはかなり難しくなります。
小学生のうちは、一緒に勉強する時間を設けたり、勉強する約束をして、習慣をつけましょう。
中学生の場合は、志望校を決めて意欲を高めるか、塾や家庭教師などの第三者の力を借りる必要があります。
勉強に集中できる環境がない
- 自分の勉強部屋がなく、リビングではテレビがついている
- 小さい兄弟がにぎやかで集中できない
などの場合、落ち着いて勉強するのは難しいもの。
特に中学生以上で、気が散りやすいお子さんは、集中できる環境を用意する必要があります。
親御さんがリビングで読書などをしていると、お子さんも勉強に取り組みやすくなりますよ。
基礎基本でつまづいている
算数・数学や英語は積み重ねの教科と呼ばれます。過去の内容が分からないと先の内容も理解できません。
基礎ができてないと、自力では学校のペースについていけなくなります。
こうなったら一人ではダメそうだね。
この場合、誰かに教えてもらうなどで、分からないところが解決する環境の用意が大切。
学校についていけるお子さんは集団塾が向いていますが、そうでない場合は、家庭教師など1対1で教わる環境が望ましいです。
勉強のやり方が分からない
勉強が苦手な場合、そもそもどう勉強すれば分からないことも多いもの。
学校の宿題や、家にある問題集が難しすぎると、自分だけでは勉強が続きません。
また、綺麗にノートをまとめるだけで、問題演習がおろそかになっている場合は、テスト本番で点数が取れないことも。
一人では勉強できない場合や、正しい勉強ができていないなら、マンツーマンで勉強のやり方から教えてもらう必要があります。
勉強を頑張って良い成績を収めると、達成感を得たり、周りから褒められます。
このような達成感や称賛は、いわば「快感」であり、勉強によって快感が得られれば、自然と勉強に取り組みます。
小さいころから勉強で親に褒められていると、この実感を持ちやすいもの。
勉強では褒めて伸ばすことが非常に大切です。
勉強できないお子さんを変える5つの方法

お子さんが勉強できるようにするには、いくつかの方法があります。
以下の方法から合うものを試してみましょう。
将来について話し、目標を見つけさせる
中学生に上がったら、高校受験について話す機会を取りましょう。
- あこがれる高校はあるか(部活や制服が理由でもいい)
- 将来やりたい仕事はあるか、そのためにどの高校に進むべきか
- そもそも進学したいのか、それとも中卒で働きたいか
このような話を通じて、「高校に進学しないといけない」「こういう高校に行きたい」というイメージが漠然と湧きます。
そうすると、「勉強をしなければいけない」というモチベーションが上がります。
この時、「いつかは自分でお金を稼ぎ、自力で生きなければならない」という現実も伝えましょう。
勉強に集中できる環境を作る
本人に意思があっても、集中できる環境が無いと、なかなか勉強には取り組めないもの。
- お子さんの勉強部屋を作る
- 勉強する時間はリビングのテレビを消す
など、場合によっては親も多少の我慢は必要かもしれません。
勉強の環境でリクエストがあれば、できるだけ応えてあげましょう。
成果の出る勉強法に取り組ませる
ノートまとめの勉強だけなど、やり方が悪い場合は、改めてもらう必要があります。
特に、うっかりミスが多かったり、問題を解くのに時間がかかる場合は、問題集を何回も解きなおす勉強に切り替えましょう。
問題を2回3回と繰り返すことで、本番でも正解できるようになりますよ。
つまづいている単元からさかのぼって勉強する
数学や英語といった積み重ねの教科では、過去の内容が理解できていないと、自力での勉強は難しいです。
その場合は、過去の単元にさかのぼって勉強しなおす必要が。
最近では市販の問題集でも、基礎から噛み砕いて勉強できる問題集(Amazon)があります。
手っ取り早いのはプロに教えてもらうことですね。
小学校なら親でも教えられそうだけど、それ以上なら任せた方が良さそうね。
成功体験をつけさせる
お子さんが自分で勉強を続けるために大切なのは、「勉強で快感を得ること」。
褒められるなどで快感を得られれば、「勉強は面倒くさいけど、やりがいのあるもの」というイメージが付きます。
そうなれば、言われなくとも自分から取り組むようになります。
勉強のプロに任せるメリット
ここで紹介した方法のうち、
- 成果の出るやり方を身に着ける
- さかのぼって勉強する
- 成功体験をつけさせる
の3つは、親が直接やるよりも、家庭教師にマンツーマンで対応してもらったほうがよいです。
特に中学生の場合は、内容が難しくなり、反抗期に入るため、親が解決するのはかなり難しいと言えます。
あなたは大丈夫?勉強ができない家庭の特徴

なお、家庭の環境が、お子さんに悪影響を与えているケースも。
以下の傾向がある場合は、親御さんも言動を変えていきたいところです。
勉強を強要して親子喧嘩になる
親が感情的になってしまったり、高い理想を押し付けていると、お子さんに「勉強しなさい」と怒ることが多いもの。
小学生ならまだ素直に聞いてくれますが、中学生になると反発して喧嘩になりがち。お子さんのやる気がますますなくなるだけです。
親も感情のコントロールが必要ってことだね。
親が放置気味で、いっさい勉強しない
「勉強しなさい」と一方的に怒るのはよくありませんが、かといって全く何も言わないのも問題。
お子さんに勉強習慣や、やる気がない場合は、やはり親からのアプローチが重要です。
- 志望校や将来の話をして、「勉強しないとまずい」と思わせる
- つまづいたり勉強方法が分からない場合はマンツーマンで教わる機会を作る
- 勉強に取り組んでいたり、成績が上がったら褒める
というステップを踏んで、間接的に勉強させるよう導くことが大切です。
小学生のお子さんなら、①勉強する約束をする②親が直接教える、でも大丈夫ですよ。
親から褒められず、自尊心がない
親から褒められたり認められることが少ないと、お子さんは自分への自信(自尊心)を持つことができません。
自尊心が低いと、努力するエネルギーが湧かず、勉強も頑張ろうとしないもの。
無気力で、すぐに諦めがちなお子さんは、自尊心が低いことが多いみたい。
こういう場合は、勉強以外のことでもいいので、常日頃から褒めてあげることが大切です。
部活や家事の手伝いなどでも、褒めるべきことをやってくれたら、言葉に出して褒めてあげましょう。
これを継続することでだんだん自信やエネルギーが湧き、勉強へのモチベーションも上がります。
規則正しい生活ができていない
- 毎日夜更かし気味で寝不足がち
- 休日は昼まで寝ている
という生活の場合、勉強に集中するのは難しいです。
睡眠時間やリズムは、親の生活スタイルに影響を受けやすい傾向が。親の生活リズムが乱れていると、子どもにも悪影響です。
可能な限り、親御さんの生活リズムも整えたいところです。
親子そろってゲーム好き
ゲーム自体が一概に悪ではありません。しかし、お子さんにとってゲームの誘惑は強く、欲望に負けて勉強しないのは避けたいところ。
子どもは親の行動に強く影響されます。親御さんがスマホなどのゲームをしていると、お子さんも同じことをやってしまいます。
口では「勉強しなさい」と言っても、その手で自分がゲームをしてるなら、「自分もゲームやってるじゃん」とお子さんに反発されます。
「毎日〇時〜〇時まではお互いにゲームせずに勉強する」という約束を親子でかわすのがオススメ。
ゲームと勉強のメリハリがつけられるので、お子さんの精神的な成長にもつながります。
病気や障害が原因の場合もある

勉強ができないお子さんのなかには、学習障害などの診断がされるケースも。
例えばこちらのサイト(LITALIKO発達障害)では、学習障害の特徴例が紹介されています。
心当たりがある場合は、一度診察を受けてみるとよいでしょう。
小児科や児童精神科、小児神経科で診てもらえます。
発達障害・学習診断を受診する方法や流れについては、以下のサイトで詳しく説明されています。
学習障害などの診断を受けた場合は、お子さんにあった勉強方法をとらないと、親子ともども苦労するだけです。
病院にて、お子さんが理解しやすい学び方のアドバイスがもらえます。その方法で勉強しましょう。
「家庭教師ファースト」など、発達障害のサポートができる家庭教師もあるみたいですよ。
原因とその対策は必ずある
お子さんが勉強できないのには必ず理由が。それに合わせた対処を取り、少しづつでも改善していきたいものです。
注意したいのは、家庭の環境が成績不振の原因になっているケース。親御さんも多少我慢して生活環境を変えるべきこともあります。
また、本人に合った勉強方法を探したり、小さな成功体験を積ませるには、教えるプロに任せた方が手っ取り早いと言えます。
平均以上の成績なら集団塾が合いますが、そうでないならマンツーマンで教わる家庭教師がオススメです。